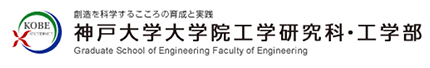第42回(令和7年度) 神戸大学工学部・システム情報学部公開講座(対面・オンライン併用開催)

令和7年10月11日(土),10月18日(土)の各土曜日(合計2日間)
受付終了いたしました。
受付期間:令和7年8月25日(月)~令和7年10月3日(金)
1. 講座の概要
神戸大学公開講座は,本学が長年培ってきた知の蓄積を社会へ還元する場として,毎年多彩なテーマで開講してまいりました。工学部は,『世界とつながる「知」の拠点,神戸でものづくり,ことづくり,そしてずっと続くしあわせづくり』という工学部ビジョンのもとで,「創造性を育む価値観の形成」を教育理念,「科学・技術の開拓と社会への涵養」を研究理念として掲げています。令和7年4月に誕生したシステム情報学部は,工学部情報知能工学科から独立し,システム情報学の各専門領域の知識や技術を応用し,俯瞰的に組み合わせることで,社会の様々な問題の解決や新しい価値の共創を主導できる人材を育てることを目指しています。本講座ではこれらの理念を体現する最先端研究を取り上げ,「知」を社会的価値へと昇華するプロセスを体験いただきます。
第42回となる本年度は,幅広い年齢層の方を対象としており,リスキリングや学び直しという目的に加え,特に高校生の皆さんの参加を大歓迎いたします。研究最前線に触れ,大学での学びやキャリアパスを具体的に思い描く絶好の機会としてご活用ください。
本年度の公開講座は6つの講義により構成され,そのテーマは,「建築・景観からまちの地域らしさを育てる」「ウェアラブルセンシングが変える医療・健康」「可視化技術を駆使し,熱流体現象の解明を目指す」「水の流れと川のかたちの不思議」「接着における界面の役割」「暗号について」と多岐にわたっています。
令和7年度の公開講座は,対面とオンラインの併用によるハイブリッド形式で開催いたします。また,学生・一般の方を問わず,受講料は無料です。これまでご参加くださった幅広い年齢層・職業の皆様から寄せられた「最新研究をわかりやすく学べた」「異分野の視点に刺激を受けた」といった声を励みに,本年度もさらに充実したプログラムをお届けします。科学と社会をつなぐ学びの場神戸大学公開講座で,新たな発見とつながりを手にしてください。
*講義日程・題目・講師及び概要はこちらをクリックしてください。
*神戸大学の公開講座のページもご覧ください。
2. 開講期間
令和7年10月11日(土)・10月18日(土)の各土曜日,
(90分×6回、1日3講義)
3. 会 場
神戸大学工学部教室
※対面形式とオンライン形式での同時開催
4. 受講対象者
一般社会人,大学生,高校生
(講義は高校生以上を念頭に置いた内容です)
5. 募集人員
対面 120名,オンライン 200名
6. 講習料
無料
7. 修了証書
6回の講義を全て受講された方に修了証書を授与します。
※オンライン参加の方には,メールに添付してお送りします。
※テキストの配布はございません。あらかじめご了承ください。
8. 受講申込み
(1) 受付期間
令和7年8月25日(月)~令和7年10月3日(金)
(2) 申込み方法
受付終了いたしました。
9. 問い合せ先
神戸大学工学部総務課総務グループ
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1
eng-soumu@office.kobe-u.ac.jp
電 話 078-803-6333 FAX 078-803-6396
10. 公開講座会場等への交通案内図
> こちらをご覧下さい。
*受講のため本学にお越しの際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
(どうしてもお車での来学をご希望の方は、事前にお問い合わせください。)
11. 講師紹介

工学部建築学科 栗山 尚子 准教授
景観とは目に映るものの見え方を指しますが,その見え方は人々や時代の考え方によって解釈が変化するため,景観のもつ意味も変化します。 神戸市には景観まちづくりに尽力してきた地域団体が存在し,多様な景観の魅力をまもり,つくり,育ててきました。 本講義では,鶴甲団地や岡本の景観を事例として,地域らしい景観の発見と表現方法,地域の魅力の可視化,ルールづくりと運用等について,お話しします。

工学部電気電子工学科 寺田 努 教授
本講義では,常時コンピュータを装着するウェアラブルコンピューティングの実現した世界を見据え,健康管理や医療などの実践的な応用技術,特に人間の状況を知るウェアラブルセンシング技術,さまざまな情報を見るウェアラブル情報閲覧技術について概説します。 技術は我々の生活や行動,心身にどのような影響を与えるのかについて述べ,人間とコンピュータの新たな関係について議論します。

工学部機械工学科 村川 英樹 准教授
エネルギーの有効利用の観点から,エネルギー関連機器の高効率化や,新たなエネルギーデバイスの開発が強く求められています。 これらの課題に対応するためには,機器内で生じる熱流動現象を正確に把握・解明することが重要です。 しかしながら,これらの現象を直接観察することは,多くの場合困難です。 本講義では、可視光では観察できない機器内部の現象を評価する手法として,中性子線や超音波を用いた手法について解説し,適用例について紹介します。

工学部市民工学科 椿 涼太 准教授
「水は方円の器に従う」ということわざがあるように,水が四角い器に入れば四角く,丸い器に入れば丸くなりますが,動き方にも不思議な特徴があります。 水の流れと川のかたちに関する物理の観点で分析を紹介します。 水を楽しむコツの一部をつかんでいただけたらと思います(写真は,水の流れを楽しんでいる一例)。

工学部応用化学科 松本 拓也 講師
接着は,身の回りから自動車や航空機の機体,建築部材に至るまで,幅広く利用されている重要な技術です。 特に近年では,軽量化による自動車などの燃費向上を目的として,高分子材料を接着剤で接着する取り組みが進められています。 材料と接着剤の間に形成される界面が接着特性を左右することが知られていますが,その界面における接着特性の発現メカニズムや原理にはいまだ解明されていない点が多く残されています。 本講義では,現在取り組んでいる接着界面の研究事例を紹介します。

システム情報学部 桔梗 宏孝 教授
日常生活において様々なデータが暗号化されてやりとりされています。 そこではどのような暗号が使われているのでしょうか。 現在使われている主な暗号と量子コンピュータでも破るのが難しいとされる暗号について解説いたします。 使われてる数学が手の届きそうな内容であるところを,楽しんでいただけたらと思います。